| 子育てコラム |
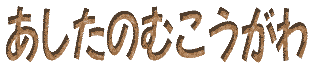 |
バックナンバー  ブログ版はこちら ブログ版はこちら |
| No. |
発行月 |
タイトル |
| 100 |
2022.03 |
30年間の社会進歩と、今懸念されること |
| 99 |
2021.12 |
社会が改めて直視すべき、非対面の不利益 |
| 98 |
2021.10 |
数字を解釈するのはなかなか難しいけれど |
| 97 |
2021.07 |
SDGsの理念は当会が「めざすこと」そのもの |
| 96 |
2021.03 |
学術会議任命拒否の容認は民主主義の放棄(2) |
| 95 |
2020.12 |
学術会議任命拒否の容認は民主主義の放棄 |
| 94 |
2020.10 |
ウイルスよりひどい過剰対策の害を直視して |
| 93 |
2020.07 |
勝手に借金で期待しながら感謝を求める教科書 |
| 92 |
2020.03 |
犬のクン付け・「彼女サン」と、相手との関係性 |
| 91 |
2019.12 |
便利な世の中になる分、劣る力にも目を向けて |
| 90 |
2019.10 |
自分で考えず「周囲と同じ」で安心する末に |
| 89 |
2019.07 |
小遣い増額と定額制で子どもが考える力を養おう |
| 88 |
2019.03 |
行為を強化してしまう、注意している「つもり」 |
| 87 |
2018.12 |
逃げ避けるだけではリスクを回避できない |
| 86 |
2018.10 |
改めて実感する、痛みや不便体験の大切さ |
| 85 |
2018.07 |
道徳教育が必然的にもたらしたアメフト問題 |
| 84 |
2018.03 |
不道徳を生み続ける宿命にある「教科・道徳」(2) |
| 83 |
2017.12 |
不道徳を生み続ける宿命にある「教科・道徳」 |
| 82 |
2017.10 |
気づいて欲しい、感謝させて感動する愚かさ |
| 81 |
2017.03 |
経験の無さからくる非寛容性とその見極め |
| 80 |
2016.12 |
より多くの「みんな」の機会均等と、落とし穴 |
| 79 |
2016.10 |
「誰が養っているのか圧力」が損なう自立 |
| 78 |
2016.07 |
みんなの意志でブラック部活からの脱却を |
| 77 |
2016.03 |
エラー防止の原点は「人は誰でも間違える」 |
| 76 |
2015.12 |
民主主義とは何かを学び直す機会に |
| 75 |
2015.10 |
今、憲法を守る姿勢が「中立の立場」ではないのか |
| 74 |
2015.03 |
同質性を求める傾向に抗うことの大切さ |
| 73 |
2014.12 |
多様性を支える科学的・多面的な物の見方 |
| 72 |
2014.10 |
小遣いにも見える、子どもの自由度の低下 |
| 71 |
2014.03 |
何を見て「道徳」を教科化しようとしているのか |
| 70 |
2013.12 |
生徒への縛りを強めるだけの「人物本位」選考 |
| 69 |
2013.10 |
数字のもつ本質的な意味を考える |
| 68 |
2013.07 |
「できないこと」をあざ笑う心が生むいじめ |
| 67 |
2013.03 |
暴力教員解雇は親の体罰へのレッドカード |
| 66 |
2012.12 |
親離れ子離れを妨げる過剰な「家族」重視 |
| 65 |
2012.10 |
伝えるのが難しい、子ども本来の集団遊び |
| 64 |
2012.07 |
社会の成熟度が問われる真の平等性 |
| 63 |
2012.03 |
平時に通じる安全防災教育の姿勢 |
| 62 |
2011.12 |
忘れ物・無くし物が激増した裏側に |
| 61 |
2011.10 |
いつまでも生徒を子ども扱いする状況の広がり |
| 60 |
2011.06 |
「ひとつになろう日本」で少数弱者を守れるか |
| 59 |
2011.03 |
支配・被支配から、敬意をもち合う関係へ |
| 58 |
2010.12 |
あっと言う間に大人になってしまう子ども |
| 57 |
2010.07 |
子の意見を聞くことと親の意志を示すこと |
| 56 |
2010.03 |
もっともっと子どもの視点で子育てを |
| 55 |
2010.01 |
文字や言葉が軽視されて起きること |
| 54 |
2009.12 |
頼らず頼られず、泣かなくなった子どもたち |
| 53 |
2009.03 |
弱者・多様性――「多事争論」との交点 |
| 52 |
2008.11 |
子ども本位の視点を取り戻そう |
| 51 |
2005.01 |
30年を経て、改めてすべての子が大切にされる子ども会を |
| 50 |
2003.11 |
「正解探し」のビミョーな風潮は まさに心の評価が生んでいるのではないか |
| 49 |
2002.12 |
小学生にも建前と本音の使い分けを強いる心の中の『評価』 |
| 48 |
2002.11 |
話し合いの手続きを大切にできない“間違った多数決体験”の蔓延 |
| 47 |
2001.12 |
子どもが微熱で少し休んでいたことを保護者は知っているべきか、否か |
| 46 |
2001.09 |
障害児を含むさまざまな子どもたちの関わりがもたらす理解と思いやり |
| 45 |
2001.04 |
過剰な自己規制が助長する自分は他人と違っていて良いと思えない心 |
| 44 |
2001.02 |
「順位なし徒競走」が醸成する風呂で裸になれない若者達 |
| 43 |
2000.11 |
一見共感できる子育て観にも少し考えると浮かぶ大きな疑問符 |
| 42 |
2000.09 |
生きる力を育むきっかけを摘まないよう親心はほどほどに |
| 41 |
2000.06 |
親しい友人グループでも一人ひとり別々に並ぶわけ |
| 40 |
2000.02 |
慣らされている現状に疑問をもちわずかな社会進歩につなげましょう |
| 39 |
1999.11 |
トイレに立った生徒を信頼した教師が無言で示した「自由と責任」 |
| 38 |
1999.10 |
「厳しい」と言われる管理主義教育こそが責任能力や判断力を損なっている |
ご批評・ご感想をお寄せください |
|
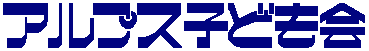 |
[コラムへもどる] [ブログ版へ] |